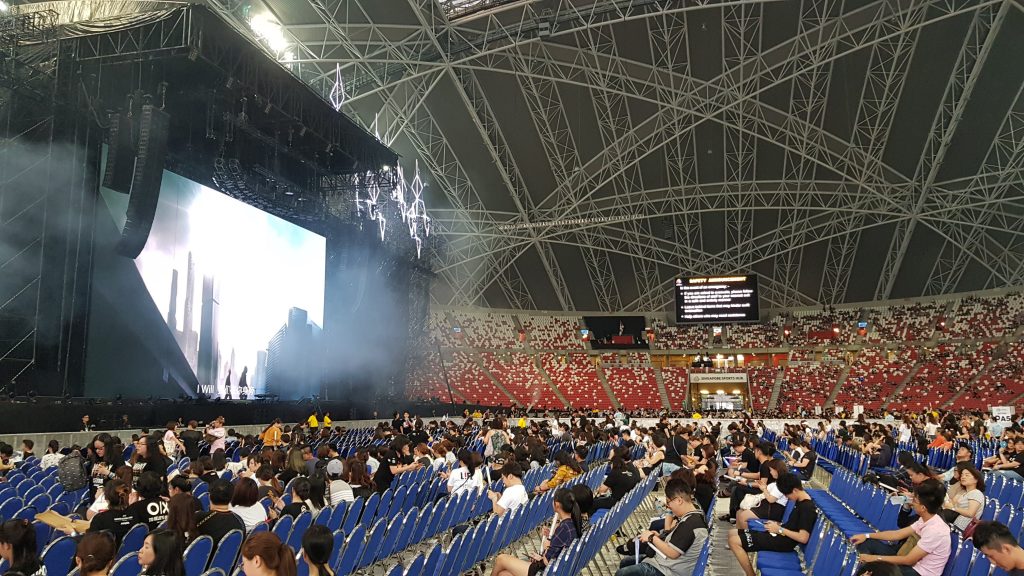なぜ従来のテスト自動化ツールはアジャイルを抑えつけるのか
やはりメンテナンス問題。思わぬところでノーマークなプロジェクトが赤くなって時間を取られるか放置してしまうかということも正直あります。
で思うに、あとで取り返せるからという理由でコストを掛けるのは無理がある。あとからもコストはかかるので借金だけが残る。なので今回で回収できるくらいで考える。
最近やっているのは、テストデータの作成を、SQLとして考えて、それを残す。SQLのメンテナンスは多くの人ができる。自動まで行かなくても、繰り返し実行ができる。検証も可能。手間は変わらないので借金を残さない。
画面入力は、本当に何度も繰り返すところはスクリプトを作る。自分でメンテナンスできる形のスクリプト。これも1日に10回×30項目くらい入力するならすぐに回収できますからね。画面変わってもすぐ直せる。
こんな考えだから大きな投資ができないのか。そこはちょっと別の問題として考えたい。投資の計画とは何か。ヒントは20%ルールみたいな話とか。
自動テストのコスト
.NETでのDIコンテナ
Unity Application Block
が、出てますよ、という記事。
http://www.infoq.com/jp/news/2008/04/microsoft-unity
で、その中で「Scott Hanselman氏は.NETのDIコンテナプロジェクトについてリスト化を始めています。」ということでリンクされているのがこちら。
http://www.hanselman.com/blog/ListOfNETDependencyInjectionContainersIOC.aspx
こういう時にSeasarが入ってこないのはさびしいですね。English Pageもあるのに。
(追記)入ってました。かるあさんありがとうございます~
で昨日はSeasar Conでしたか(過去形)。
ビデオ見ましょうか。
http://event.seasarfoundation.org/sc2008spring/Streaming
(ちょっと重いですよね・・・)
App Engine 開発環境
まだ招待してもらえませんが、ぼちぼちたくらみ開始。
統合開発環境(IDE) まずここから。
PyScripter
SPE IDE
Pydev
それぞれの紹介記事として、
Python開発統合環境の決定版!
Python のスレッドについての資料と Python の統合開発環境 (IDE) – 傀儡師の館
Fomalhaut of Piscis Australis : [ python ] Eclipse に PyDev をインストールする
など。
ぱっと見は、PyScripterがよいような気がする。きっとRubyにおけるRDE。しかし、ここはあえてPyDevにしてみます。macでもやるかもしれないので(たぶんやらないけど)、Delphiというのがやや残念。
Python Python は普通に最新の2.5.2
Eclipse PyDevを使うということは、Eclipse。起動してみると3.2でしたが、どうやら世間の皆さんは3.3.xのようです。特に使ってるわけでもないので、前に入れたものを最新版に入れ替えようと思ったのですが、All-In-One Eclipseは3.2.0ベースとのことで、しかもリンク先の様子がおかしい。ということで、今回はAmaterasIDE Installerにしてみます。
起動したら、PyDevの設定。
Fomalhaut of Piscis Australis : [ python ] Eclipse に PyDev をインストールする
ITmedia エンタープライズ:Eclipse+PyDEV=Python統合開発環境
などを参考。
App Engine
さらにApp Engine環境としてSDK。
http://code.google.com/appengine/downloads.html
最初の一歩 まずはこちらを参考に、超基本から。
http://builder.japan.zdnet.com/sp/google-app-engine/story/0,3800086196,20371257-2,00.htm
と言いつつ、いきなり
socket.error: (10013, ‘Permission denied’)
というエラーではまりましたが、IISでポート8080を使ってしまっていたからでした。そちらを止めると無事画面表示ができました。
ちなみに、下記WARNINGは気にしなくてよいようです。
WARNING 2008-05-24 13:01:01,667 datastore_file_stub.
看美女
昨日の帰り際、Oくんに軽く中国語を教えてもらいながら、自分のGoogleReaderに登録してある
http://www.cnblogs.com/beginner/
を眺めていたら、技術系ブログ集には異色な「看美女想到的」なる文字が。
内容は、美女をを見ると、心臓がバクバクし、脳があれこれ考えだすのは、オブザーバパタンみたいだね、ということの実装で、たわいもないといえばたわいもないのですが、タイトルに惹かれて翌日実行までしてみた自分が一番たわいないです。
パターンの説明はやはりこれが一番分かりやすい♪
http://www.hyuki.com/dp/cat_Observer.html
–広告–
広告
ドラッカー、もう少しです。
テクノロジストの条件 (はじめて読むドラッカー (技術編))
P.F.ドラッカー 上田 惇生
イノベーションを生み出す7つの機会の一つとして、ニーズの存在があるという話の中で、マスコミ(新聞)を生み出したのは、大量印刷のための自動植字機と広告であるという話がありました。広告という社会的イノベーション。
IT・情報システムに対するコストの許容性とは、本当のところはどの辺なのか。
1システムウン百万円・ウン千万円は、全然OKなのか、それとも1業務十万円なのか、あるいは会計ソフト5万円・1万円の世界なのか。それとも、広告付き0円なのか。
業務システムでも広告付き、ありじゃないですかね。まあ、大企業とかだとそれ以上のこともできると思いますけど、あとはまさに企業家精神を持ちうるか・やるか、という問題ですね。
【ということで広告(の広告みたいな)】
<img alt=“あなたのホームページ・メルマガで広告収入!” 【アクセストレード】 src=“http://www.accesstrade.net/at/r.html?rk=010002mh0044mz" border=0>
INETA Day 2008
会社のYくんと参加。社内ブログで募って一人だけというのはややさびしいですが。
http://www.ineta.jp/tabid/173/Default.aspx
小島さんはさすがです。ナベアツそこまでやりますか。自分のナベアツが思いっきり手続き指向だという再認識。手続的-宣言的-図解的という視点(特に図解的をこう並べるというところ)も、当たり前のようでいて新鮮。
懇親会のコミュニティ紹介も面白かったです。
松崎さんも、話を聞くのは2回目でしたが、やはり面白かったです。ロードテストはもっと使うべきですね。
SQL Server 2008情報も盛りだくさん。
みんな来るべきだったよ~
MoneyLook
大分時間がたってしまいましたが、とりあえずMoneyLookはたまに眺めてます。
ゆうちょも昔の定期貯金が自分でも訳分からなくなってるのでちゃんと管理したいのですが、そこまでが面倒なんですよね・・・。
ところで、上のバナーはアフィリエイトですが、無料ツールの広告に金を出して、それでも儲かっちゃうというのがすごいなと思います。確かに、ログインすると色々な金融関係の広告が表示されますけど。
ドラッカーによる原価計算改善案
ドラッカー、さすが、ここに触れてくれるとは。でも、なんでもっとこの辺を頑張ってくれなかったのだろう。
現行原価計算の問題を4つの欠陥として挙げています。
ぶっちゃけて言えば、直接の労働費、どんだけよ。単価いくらか知らないけど、給与として払っている以外は、単にその他経費を直接労働に比例させているだけでしょ。通常のオーダ外のことをしているときのコストはどうなってるのよ。
そんな問題意識です。
で、その解決法として、時間ごとの固定費というものを出してきます。ちょっと分かりにくいです。が、要するに変動費でないものを変動費としてとらえていることによるいびつさが問題なのだと思います。材料を増やせばものがたくさんできるからそれは変動費でしょう。しかし、知的生産においてはテーマは品質です。時間をかければ比例して品質が上がるか。よい機械を使えば比例して品質が上がるか。上がらないなら変動費ではないでしょ。
ここの考えを変えることで、人間も変わってくると思うんですけどね~
テクノロジストの条件 (はじめて読むドラッカー (技術編))P.F.ドラッカー 上田 惇生 by G-Tools
TAMACHI.LT
行きたかった!DDDで頑張ったのに!悔しいですっ!!(By ザブングル)
昨日はTDD(停電ドリブン開発)。これは結構効きますね。トリンプの、時間で電気を消す作戦の効果が想像できます。
知識労働の生産性
だてにドラッカーではないですね。濃いです。
テイラー以前は、生産性の向上は技術と道具によってもたらされるものであり、労働については、より激しく働くか長く働くかしかなかった。
しかし、テイラーは肉体労働の生産性を向上させた。その手法は
1.仕事を個々の動作に分解する
2.各動作に要する時間を記録する
3.無駄な動作を探す
4.不可欠な動作を短い時間で簡単に行えるようにする
5.各動作に必要な道具を作りなおす
これは、成果が大きいだけでなく憎まれもしたので、いろいろな名前の手法が現れたが、日本のカイゼン含めて、この手法が使われている。
では知識労働の生産性はどうか。
まず、肉体労働において質は制約であるのに対し、知識労働においては本質である。教師の仕事は生徒の数で評価されるのではなく、生徒が本当に学んだかどうかによる。
しかし、仕事の質が何かを定義するのは難しい。なぜなら、そもそも仕事が何かを明らかにすることすら難しいから。
なお、知識労働者は知識労働にのみ携わるわけではない。知識労働と肉体労働の両方を行うのであり、そのような人達を、テクノロジストと呼ぶ。
・・・こんな話ですが、私たちもテクノロジストだったんですね。これは当たり前のようですけど、ちょっと新しい視点でした。
そして、肉体労働についてはテイラーの手法を適用できるわけです。適用しているわけです。
仕事が何かの定義が難しいのもまさにそのとおり。例として、看護師が、仕事を患者の看護とする人と医師の補助とする人がいるが、少なくともいわゆる「雑用」が生産性を阻害しているという点では一致して、それを取り除くことによりよい効果が出たという話があります。しかし、現実には、このレベルさえ、場面場面ですり替えられるわけです。すなわち、ある時は、患者の満足度を向上させろ、ある時は、医師の満足度を向上させろ、ある時は、雑用も自分の仕事を向上させるために必要な立派な仕事だ・・・。
結局、本質部分での生産性向上を見せてあげないと、雑用からすら逃れられないんですよね。そしてその生産性を質で測るとすると、結局は顧客満足度の向上だったりするから、テクノロジスト自身では見せてあげにくい、ということかなぁ。
・・・と一瞬逃げたくなりましたが、第一に、いきなり質で生産性を評価しようとする人は(良かれ悪しかれ)あまりいない。既存の枠組みに従えばよいと考えれば、いろいろ手はある。
第二に、そもそも、材料なくして提案は無理。あとの方でドラッカーも書いてますが、日本で提案制度が成功したのは、その導入がSQC確立の後だったからとのこと。もちろん、知識労働におけるSQCとは、というところは努力が必要ですが、諦めて嘆いても仕方がないということかと。
—
今日は天気がよかったので、無駄に下総中山まで出かけて、こんなことを考えていました。明日から仕事ダァー